ノーベル文学賞を受賞したイギリスの作家カズオ・イシグロの代表作。
と思っている人も多いかもしれません。
しかし本作はとても読みやすい内容で、おそらく多くの大人の心に響く小説だと思います。
事実、私も同じ理由で読むのを敬遠していたんですが、読んでみると最初の数ページで主人公に好感を持ち、気づくと惹き込まれるように読み進めていました。
そして読み終えた時には「人生で読んだ小説ベスト10」に入れようという気持ちになっていました。
ぜひ、一生に一度は読むべき作品だと思います。
本記事は未読の方向けに書いていますが、既読の人も理解を深める助けになるような情報を記載しています。
目次
あらすじ
あまり海外純文学に馴染みがない人向けに、ざっくりとわかりやすくこの小説の概要を述べるならこうです。
名家に仕える愛すべき「超有能マジメ執事」が、イギリスの田舎を旅しながら感傷に浸って人生を振り返る、美しく切ない物語。
この超マジメな執事である主人公がなかなかに愛すべきキャラクターで、彼の存在なくしては、このすばらしい物語は成立しません。
愛すべき主人公スティーブンス

主人公であるミスター・スティーブンスは、こんな人です。
- 超名家に仕える誇り高い執事
- 十数人もの使用人を束ね、職務計画をとりまとめる敏腕執事
- 雇い主への揺るぎない忠誠心
- 一見カタブツに見えて、実はすごく人間らしい一面がある
- マジメすぎて逆にかわいいところがある
彼の雇い主であるダーリントン卿は、イギリスの政治や外交に関わる重要人物で、お屋敷には各国の重役や著名人が度々訪れ、政治に関わる重要な外交会議が頻繁に行われます。
ちょっとしたミスや粗相が世界情勢に影響するというピリつく環境の中で、十数人もの召使いたちに指示を出しながらテキパキと仕事をこなします。
こき使われようが、馬鹿にされようが、理不尽な仕事をやらされようが、感情を抑えて職務をまっとうする、プロの執事なのです。
しかしその超マジメな性格の裏に、彼らしい人間らしさが見え隠れするのがこの作品の魅力です。
例えばこんな点。
長年イギリスの名家に仕えてきたスティーブンスが、新たな雇い主としてアメリカ人の主人に仕えることになった後の話です。
高貴で伝統的なイギリスの家柄では、厳格で礼儀を重んじた主従関係が一般的でした。
しかしどうやらアメリカでは、主人と使用人がジョークを言い合いながら友好な関係を築いていくのが一般的らしいと知ります。
雇い主を楽しませるのも執事としての大事なお仕事
と考えて、毎日ラジオを聞いてジョークの研究をするスティーブンス。
マジメ一辺倒のイギリス人執事がジョークの練習…。
なんとも言えないけなげさです。
そして彼の渾身のジョークが、まあスベるスベる。
彼なりにスベったことを落ち込むのですが、それでもマジメなので、ジョークの勉強をやめる気はないのです。
旅をしながら人生を振り返る
そんな主人公が、休暇をもらって数日間のドライブ旅行に出るのがこの物語のあらすじです。
行く先々で目にする美しいイギリスの田園風景を目にしながら、スティーブンスは自分の人生を振り返ります。
- 執事として品格を身につけるまでの数々の経験と、さまざまな失敗。
- 同僚の女性に抱いていた不器用で淡い恋心。
- 屋敷を訪れる様々な重要人物たちの外交会議。
これらの物語は、スティーブンスの「仕事論」であり「品格についての美学」であり「人生論」です。多くの人々が彼の言葉に共感したり反発したりして、感情を揺さぶられるはずです。
また一方で、この物語はスティーブンスの目を通して語られる「歴史ドラマ」でもあります。
当時の世界の動きを読み取れるという点で、作品として価値の高いものになっています。
時代背景を解説
読む前に知っておくと良い、時代背景について簡単に解説します。
スティーブンスは、第二次世界大戦が終わった後のイギリスを旅しながら、回想するかたちで過去の出来事を語ります。過去の回想のメインとなるのは、第一次世界大戦と第二次世界大戦の間に起きた出来事です。
第一次世界大戦後、敗戦国であるドイツは多額の賠償金を請求されることになります。その額は、当時のドイツにはどう考えても返済不可能な「天文学的数字」だと言われていました。
それによって不況になったドイツ経済は、のちの世界恐慌の原因の1つにもなったと言われています。
また、経済を立て直すべく台頭して英雄となったヒトラーが、のちに第二次世界大戦やユダヤ人虐殺など様々な負の歴史的出来事を引き起こしたことも事実です。
- 財政難に苦しむドイツ。
- 戦争による損害も少なく、お金持ちで余裕のあるアメリカ。
- 再び戦争が起こることを懸念し、ドイツへの宥和政策を進めたいイギリス。
- ドイツに対して特に過酷な制裁を強いていたフランス。
こうした中、2度目の戦争を回避するためにもドイツへの対応を緩めてあげたほうがいいんじゃない?という話し合いが、スティーブンスの仕える屋敷「ダーリントン・ホール」で開かれるのです。
世界史で知られている通りドイツに対しては宥和政策が進められ、その結果第二次世界大戦が起こるのを遅らせたと言われています。
しかし、ヒトラーは逆にこれを好機と見て大戦に踏み切ってしまいます。
ドイツ側に友好的な立場をとっていたダーリントン卿(スティーブンスの雇い主)は、知らず知らずのうちにナチス・ドイツの手駒として利用されるようになってしまうのです。
そんなダーリントン卿を慕って、献身的に仕えていたスティーブンスの心境は、複雑なものです。
スティーブンスの「当時の心境」と、過去を振り返った上での「現在の心境」を重ね合わせながら語られる物語は、人生の難しさ、複雑さを訴えてきます。
考察・感想

物語は、大きく分けて2つのテーマで語られています。
- イギリスと諸外国の力関係の変化
- スティーブンス個人が感じる人生の難しさ
『日の名残り』は、歴史や社会といった大きなスケールの問題を描写しながら、個人的な人生論を語る作品でもあります。
その2つのスケールを上手に織り交ぜて、全体的にまとまりのある落ち着いた雰囲気に仕上げているところが、この作品の素晴らしいところです。
失われ、変化しつつあるイギリス
欧米間の外交調整の中心的存在だったイギリスは、戦争を経て力を失っていきます。
由緒あるイギリスの伝統的な屋敷も、アメリカ人に消費される過去の遺産になりつつあります。
ヘンリーが旅を通して見る風景の描写は、「イギリスの田園風景はこんなに美しいのにな。あの頃のような国としての輝きは、失われつつあるんだな。」という嘆きを表しているように思えます。
また、有力な貴族たちが政治を動かしていた時代から、より民主化を求める声が強くなり、村人が政治に意見することの重要性を説く人物が出てきます。
彼らの叫ぶ民主主義には弱点と矛盾があることをスティーブンスは理解していますが、彼自身の経験を踏まえると、複雑な想いが渦巻くのです。
伝統や価値観など、さまざまな点で変化していくイギリスの様子が描かれています。
暮れていく人生への想い
スティーブンスの人生は、偉大な雇い主に仕えていると信じて疑わず、私情をはさまず、同僚の女性への恋心も殺して、仕事一筋で貫いてきた人生でした。
自分を殺して仕事に専念してきたスティーブンスの人生は、どこか美しく惹かれるものがあります。
彼なりに品格のある誇り高い人生を送ることができたと思っていたスティーブンスですが、旅の途中で人生を振り返るにつれて、後悔や反省の気持ちがあふれてきます。
自分の生き方が間違っていたかもしれないことを嘆き、後悔にのまれそうになるのです。
しかし、人生はやり直すことができません。
その後悔と共に感じるなんとも言えない切なさと、眼前に広がる夕方の風景と、そばで励ましてくれるおっちゃんのやさしいセリフが胸に沁みるのです。
過去はどうあれ、自分なりに懸命に生きてきたことを温かく讃える、心に残るラストです。
スティーブンスの抱く想いは、時代を超え国を超え、様々な人の人生に通じる普遍性があります。だからこそ、多くの人の心に響く作品となっているのだと思います。
映画版について:原作との違い
1993年にアンソニー・ホプキンス主演で映画化されています。
ストーリーは概ね原作通りですが、スティーブンスの描かれ方が異なっていて、印象がかなり違って見えます。
原作はスティーブンスの一人称語りなので、当然スティーブンスの心情描写が多く、心の葛藤や感情の機微が丁寧に描かれています。
映画では、スティーブンス含め登場人物全員を客観的に映すので「第三者から見たスティーブンス」という印象が強く、原作よりも無感情で、より冷徹な印象が強いです。
原作では人間性が垣間見られて親しみやすい部分がある一方で、映画のように視点を変えれば、周りからは冷徹な人だと思われていたかもしれないことも事実です。
「視点を変えると、物事や人の見え方がガラリと変わる」という点は、本作のストーリーから感じるテーマの1つでもありますが、原作と映画の違いがその良い例になっていて面白いです。
歴史にも人にも多面性があって、さまざまな視点から物事を見ることの大事さを感じます。
「スティーブンスをどう捉えるか」で、人によって好みは分かれそうですが、できればどちらも鑑賞して、違いを味わってみるのがおすすめです。
ちなみに個人的には原作の方が好きです。
ラストシーンの温かみは、原作にしかない持ち味です。









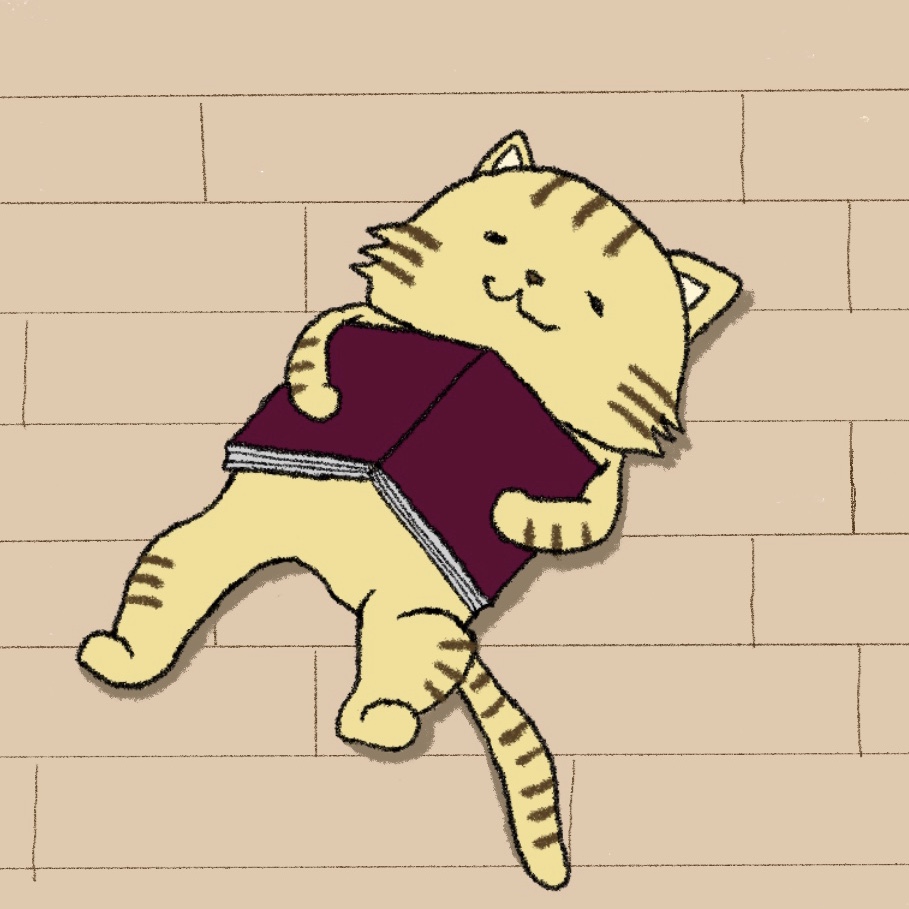
海外の純文学なんて、堅苦しくて難しそう